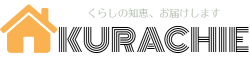気になる生ゴミの匂い
日々の生活でどうしてもゴミは出てしまうものです。
特に生ゴミは匂いも気になりますし、どうやって管理をすれば良いのかを考えることが必要なものでもあります。
日々の生活の中で出てきたゴミを毎日捨てることができれば匂いやコバエといったものを気にせずにすみます。
しかし実際にはゴミの収集日は自治体によって決められたものがあり、その日にしか出すことができません。
そこで、自宅で保管している間に匂いが気にならずに管理ができる方法を身につけておきたいものです。
生ゴミの匂いの元となる雑菌
匂いの原因となるのは雑菌があります。
そこで、雑菌が繁殖しやすくなる条件を知りそれを断ち切ることが重要です。
雑菌が繁殖しやすくなる条件となるのが湿気と温度です。
そのため梅雨から夏にかけての季節が最も匂いが気になる時期として挙げられます。
そこで、生ゴミの処理として水気を切ることが大事になってきます。
三角コーナーにゴミを入れておくと水気が溜まりやすいので、捨てる前にはゴミの水分を減らすことが重要です。
可能であれば生ゴミを乾燥させて捨てることができれば匂いの元を大幅に減らすことができます。
調理中に出てきた生ゴミを晴れた日に外に出して乾燥させてから捨てることで匂いがかなり減らせることができるのです。
ただし雨の日もありますし、梅雨の時期は外に出している間に乾燥せずに余計に匂いが発生してしまうことがあります。
その時に有効なのが、ゴミの水分を切るためにオススメなのが生ゴミを新聞紙に巻いて捨てるという方法です。
新聞紙が水分を吸収するだけでなく匂いも吸収してくれるので匂いを抑える効果があります。
お酢を使って匂いを消す
お酢は酸性のものなので、アルカリ性であるアンモニア臭や生ゴミ臭といったものを中和させて緩和することができます。
お酢は水で2倍ほどに希釈して使います。
生ゴミに直接ふりかけても良いですし、生ゴミを入れる袋の中に新聞紙やキッチンペーパーにお酢を染み込ませたものを敷いておくのも有効です。
ただし、中にはお酢の匂いが苦手という人もいます。
その時にはクエン酸水を使用するのがオススメです。
クエン酸はお酢の中に含まれている成分なので、クエン酸水にすればお酢と同じ効果が得られるものを作ることができます。
もちろん忙しくてクエン酸水が作れないという時にはクエン酸を生ゴミにふりかけるのでも問題ありません。
小さじ1杯ほどふりかけて新聞紙に包んで捨てることで十分に効果が得られます。
同じくカビや雑菌を減らすことがあるものとしてエタノールや重曹といったものもあります。
捨てるものや匂いの種類で使い分けることでより匂いが抑えられるようになります。